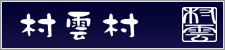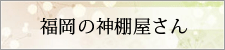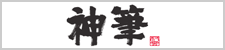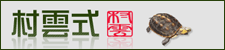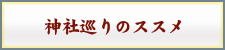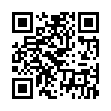- 2019-04-25 (木) 14:34
- 神社
つづき。
さて、長い長い「鳥居→参道を歩く」の話が終わりまして、ようやく『手水舎(ちょうずや)』の前へ(;´Д`)
この読み方は「ちょうずしゃ」でもいいですし、「ちょうずや・・てみずや・てみずしゃ」でもOK!自分はもっぱら、「てみずしゃ」派です!初めにてみずしゃで覚えたので、言い易いっていうだけの理由で(笑)
「手水の使い方」
1.左手に柄杓をもって、水を満タンに注ぎます
2.そのまま、柄杓の水(1/3以下)を右手に掛け洗い、今度は柄杓を右手に持ち換え、これも1/3以下の水で左手を注ぎ洗います
3.残った1/3以下の水を、そのまま左手に移し、口元まで持っていき口をすすぎます
4.すすいだ水を下に出すのですが、口元がみえないように左手で口を覆うと上品ですね!
5.口をつけた左手をすすぎます
6.柄杓の持ちてを洗う感じで、柄杓を地面に垂直に立て、残った水を下まで流して終わりですっ!
※すみません、一部修正です(-_-;)(2019.5.2)
ポイントは、、、、、
○柄杓の水を使いすぎないこと。途中で無くなったらさらに追加してOK!ですが、出来れば一回の水で終わらせるとスムーズですし、次の方が待っていれば邪魔になりません(´ー`)
○中にゴミが落ちないように、柄杓を置く時は伏せておきましょう
○間違っても柄杓にそのまま、口を付けないようにっ!!!
日本人って何が凄いかって、絶対に「他人(次に使う人のこと)」を考えているんですよねぇ、、、手水ひとつ、とっても。
水を吐く時は周りに散らないように口に手をあて、最後に柄杓を立てるのも自分が使った持ち手を洗う意味合いで柄に水を滑らせる。
(慣れないとこの時は水、ほとんど残っておりませんが、この最後の作法されている人をみると素敵なだなぁ~と感心します。。。。)
柄杓を置く時も、次の方を考え、なるべく柄杓の中に異物が入らないように気を使う。
いや~素晴らしい、、、、、、、
ちなみに、手を拭くハンカチが持てない状態ですので、管理人の場合はちょっと行儀悪いですが、予め脇に挟んでやってます・・・・最近、キレイな手拭きがさがっている神社の方が珍しいので(;´∀`)
反対に、手水舎の手拭きがキレイな神社は
「すっげー行き届いているなぁ・・・・」
なんて感心してますが。
神様に挨拶に伺います。
偉い人や大切な人に会う時も同様、手が汚れていたり爪が伸びている事って少ないですよねぇ~物理的な清潔感と共に、実はここ!が大切で、神道は『心身の清浄感』が大切です!
今でも神社のご奉仕前には、ちゃんとした神社では朝一番で『潔斎(けっさい)』を行います(´ー`)
大きなお風呂で、体を清める・・・・と同時に、心も洗い流し、いろんな想いやモヤモヤした気持ち、憤りや悲しみなどをリセット(浄化)するんです。
それを参拝の都度、参拝者に要請するのは難しいので、、、、、
代わりに、『手水舎』を造って、そこで心身の清浄を願う!
昔は、大きな神祭の際には、そこまでの色んな想いや今からの不安などを近くの神社で天津祝詞を挙げて来い!ってか感じで祈らされておりましたが・・・・・今、考えるとこれも「潔斎」の考え方に近かったのかなぁ~と思います。
鳥居での一礼が終わり、参道を歩いて気持ちを清らかに保ち、内境内(うちけいだい)に入る前に締めで手水舎で心身を清める。(手水舎がない&水が入っていない場合はペットボトルの水を準備でも構いませんよー)
ようやく立った、『ご神門(ごしんもん)』の前。
「ご神門」の呼び名の他に、『楼門(ろうもん)』と呼ばれることもございますが、これは何が違うかと申しますと、楼門はそのまま左右から回廊と呼ばれる屋根付きの歩ける道が存在しております。
福岡だと、筥崎宮さんや糸島の櫻井神社さんなどは、楼門と呼びますね(´ー`)
住吉神社さんはご神門、櫛田神社さんは微妙だけど、、、、あれも楼門に入るのかな。
ご神門(楼門)をくぐる前に、もう一つポイントが。
ご神門や楼門の前に、狛犬がいたり、大きい神社になりますと『随神(ずいしん)』と呼ばれるお侍様の大きなご神像、見たことありませんか??
(これがお寺だと阿吽の仁王像も多いようですが)
この方々、実は列記とした「神様」なんです!!!
その神社にお祭りしている神様の、門番的な役割の神さま。南北朝時代に絵を書いて門に貼ったのが起源とも言われております。
お名前もちゃんと付いてて、
「豊磐間戸神(とよいわまどのかみ)」
「櫛磐間戸神(くしいわまどのかみ)」
向かって右が豊磐間戸神様、向かって左が櫛磐間戸神様って教えて貰ったのですが、、、、ここが記憶が曖昧でして(汗)
※誰かご存知の詳し~い方がいらっしゃいましたらコメントでお願い致します(;´∀`)
で、神様にどうしても好かれたい管理人は、
「いつもありがとうございます~♪」
なんて気軽に声を掛けさせて頂いております!
(名前憶えてないけど、ここポイント!!(笑))
随神様にお声かけしつつ、ここでも一礼してようやく境内に入ります、、、、、
文字に起こすと長い(苦笑)
つづく。
- 次の記事: 新・正しい神社参拝のススメ③
- 前の記事: 新・正しい神社参拝のススメ①
コメント:2
- 匿名 19-12-11 (水) 14:39
-
えーっと、ずいぶん前の記事におじゃまします、、。御神門は向かって右は櫛磐間戸命様、左は豊磐間戸命様、だったと思います、
御神門の前で、右→左→正面の順で小揖でご挨拶だった、かと、(^_^;) - 管理人 19-12-12 (木) 3:11
-
匿名さん
こんばんは、匿名さん。そして、コメントありがとうございます!!ちなみにご神名が記載されている書物などご存じないですか・・・?昔、一度読んだ記憶があって書名がどうしても思い出せない・・・・