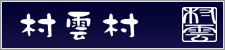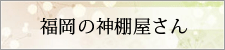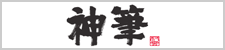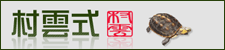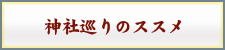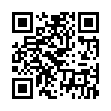- 2016-11-11 (金) 13:34
- その他
「国風歌舞」 と書いて、「くにぶりのうたまい」 と読みます。
日本びいきの管理人としては、もうこの漢字から感じる古い日本語の美しさ、語呂のセンスのよさとカッコよさだけでかなり心をひかれております・・・・ミーハーなのです(´▽`*)
もともとこの国の成り立ちのなかで、「力あるもの」がその地を治めていたわけですね(´ー`)
この場合の「力」とは、武力だったり統率力だったり、知力だったり魅力だったり、、、、すべて含めたマンパワー。
いわゆる、「運」と呼ばれる「神様からの寵愛」 も含めてもよいカモ?しれません(´▽`*)
各地の「力あるもの」がそれぞれの”想い”を胸に、戦いと滅亡、和合と離反のくりかえしでして。これは、今まで記事にした「神様物語」を読んでもらった方がいいかも知れませんね~
(余談ですが、おそらくこの縄文時代~古墳時代~飛鳥時代にご活躍された方々の”一部”が、ひょっとしたらそれ以前の方々が、いまなお神話として残り、皆さんが大好きであろう 「血肉をもった神々様」が活躍しまくっている時代です。今では日本全国で学業の神様としてご信仰を集め、生きた人間として平安時代にご活躍されたあの「菅原道真様」でさえも、まだまだ若い神様になってしまうわけですね・・・・・(;・∀・))
連合したり、分裂したり、協力したり戦争したり。
弥生時代にはすでに大陸(今の中国や朝鮮半島)での渡来や交流も各小国ごとにあったようです。
当時、中国大陸や朝鮮半島はかなり文化が発達しており、その技術や文化に驚いたにちがいありません(´ー`)
持ち前の、倭人特有の 「よし、追いつかなければっ!」 という前向きな向上心が燃えたぎったのは容易に想像がつきます(笑)
100以上の小国が集結してそのうち、
「メインを一つの頂点として、そこに力を集約させて小さな国をまとめよっか?そっちの方が便利じゃね??」
と、たぶん、どこかの誰かがいいだしまして。
集結した100以上の小国の連合国(政治集団)の場所はこの地、「福岡」 にありまして場所は今のところ諸説ございますが、ある一説では「北九州」と推定されております。
(ちなみにこの連合国の盟主は、倭人の奴国。奴国とは今の福岡平野ですね、、、、これは当時の中国(後漢)が勝手に決めた名前で管理人的にはあんまり好きじゃない名ですが(;・∀・) 福岡市東区の志賀島からみつかった『金印』には「漢の奴の倭の国王」と彫られており、最初の歴史書に載っている奴国王は、「帥升(すいしょう・ししょう)」と呼ばれていた、名前か、役職の人です~)
「100以上の小国をまとめた、連合国”倭国”」 といっても、しょせんは烏合の衆。各地の豪族のあつまりです。
弥生時代の後期には、王位の後継者争いか、各小国同士の「誰が頭をはるか?」の争いなのか・・・・・そこそこ大きな内戦がおきます。
なぜ「王位継承」か、「代表権」の取り合いと二つにわかれるのか?
それは「倭国」の一言ではまとめられない、各地の「国」が存在していたことを後漢書に記されているからです。
現在の佐賀県の吉野ケ里遺跡では、大規模集落跡、ムラの周りには物見やぐら、争いで亡くなったとおもわれる矢じりが刺さったままの人骨が多数発見されております。
余談ですが、そういえば大昔にはじめて吉野ケ里遺跡に行ったとき、管理人も当時の服装で、当時の料理をアレンジしたものを食べさせていただくという弥生人になってみました~ありがたいことに、頭に矢じりは刺さりませんでしたが(´ー`)
その面倒くさそうな争いを集結させて、倭国の内乱をおさめたのが、これも教科書では有名な邪馬台国の女王、 『卑弥呼』 さんです。
卑弥呼さんの後は、男子が国を治めたらしいのですがこれも反発の元になり、さらに内乱、、、、といって良いのか、さらなる国の奪いあいか?
結局、卑弥呼さんの宗女(正統・嫡子)である、「台与(とよ:表記・読み方には諸説あり)」が13才の若さで盟主の座におさまり、ついでに国も治まります。
この、卑弥呼さんの跡継ぎの「台与」さん、佐賀の與止日女神社(よどひめじんじゃ)のご祭神や、福岡の櫻井神社・與止姫宮に祀ってある神様ではなかろうかと、いわれております・・・・・・
長いな、、、、まだまだ本題にたどりつかない( ;∀;)
つづく。
- 次の記事: 国風歌舞(くにぶりのうたまい)とこの国の成り立ち②
- 前の記事: ポジティブシンキングとスランプ
コメント:2
- 北斗七星 16-11-11 (金) 14:14
-
よい話ですのー。
書くべき時なのですねぇ。。(^ν^) - 管理人 16-11-12 (土) 22:01
-
北斗七星さん
いつか自分の、龍笛生演奏を聴いてください^ ^ それまで必死に練習しておきますんで( ´ ▽ ` )ノ