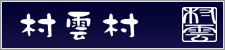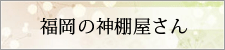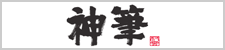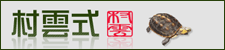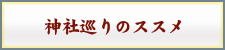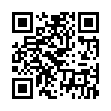「神楽と雅楽①」 につづきまして、今回は 『浦安の舞』 に特化した話ではございますが、、、、、
1940年(昭和15年)、神武天皇即位2600年(皇紀2600年)を記念して、多忠朝(おおのただとも)先生が作曲・作舞した神楽でもございます。
※多忠朝先生は、当時の宮内省楽部楽長さんです
歌詞は昭和天皇の御製といわれております。
天地(あめつち)の神にぞ祈る朝なぎの海のごとくに波たたぬ世を
「朝日に照らされる凪の海のように、波ひとつなく清浄な世のなかを天と地の神々様に祈ります」
時は日中戦争の真っただ中・・・・・
不況にあえぎ、先のみえなかった日本のなかでもう一度、平和な世を願いつつ、神様によろこんでいただき、また神様と一体になろうと、日本全国はもとより、朝鮮や台湾にも講師が派遣され朝の10時に一斉に奉奏(ほうそう)されました。
天皇陛下からのご指示で、全国のほとんどのメジャーな神社で舞われた舞なんですね^^
5年後の昭和20年に終戦をむかえ、GHQが介入してきた後もこの舞はけっして失うことなく、今でも全国の神社では舞われておりますし、神職のなかではその存在を知らない人はいないと思います。
しかし、これが歌だけでもかなり難しい・・・・・・
基本的に神楽と呼ばれるものは「節」がないものが多く、耳で覚えるしか方法はございません、、、、、
それにどうにか、こうにか、雅楽器(和琴・龍笛・笙・百拍子など)を後づけしたものがほとんどで、、、、、特に浦安にいたっては演奏者泣かせで有名です(-_-;)
それにしても、なんと意味のある歌詞かと。
作られた過程もさることながら、そっちの方でいたく感動してしまう管理人でございます。
以下はマメ知識ですが(^^)
全国的に有名な舞、「浦安」や「高砂」は有名ですが、その他に各神社で残されている舞は数多いです。
とくに、福岡の城南区にある田島八幡宮の 『田島神楽』 は無形民俗文化財にも指定されており、旧暦6月1日には神社の規模にかかわらず(小声)・・・・かなり多くの人たちで賑わいます!
この神社には、昔々のその昔、隣に流れる樋井川がよく氾濫しておりまして、そのため、氾濫のたびに人身御供(今ではありえない生贄・・・・・)が捧げられていたとか。
「これでは村の人口が減ってしまうっ!!!」
ということになり、神様におうかがいを立てて代わりに数多くの”神楽”を奉奏させていただくことでケリがついたとか・・・・・
・・・・・ってどんな神様だよっ!
(結局は生身の人間の都合なのです・・・・・・・・・)
これらの神楽は「出雲系神楽」の特徴との類似点がおおく、この辺りが管理人としてはとても興味がそそられる話でもございます~
※神楽も時代と研究者によって、さまざまな分類がございます!
話がそれて、ここからが長くなりそうなので・・・『浦安の舞の話』 ということで、今日はここまで(^^)/
暑いからみなさん、熱中症に気をつけて!
- 次の記事: にゃんにゃんのじいちゃんの命日につき。
- 前の記事: 神楽と雅楽 ①
コメント:3
- ブーシュカ 16-07-07 (木) 19:33
-
雅楽に作曲ってあるんですねぇ。奥が深いデス。きみがよも、和歌をアレンジしたとかいう説を聞きかじった記憶があります。節がなくて、演者泣かせとか、聞いてみたいです。常に太平の世を願い、そして無意識にも、それに汗をかく方々が日本各地におられることをありがたく思います。
国々をまたいでの事柄も最近は家庭の話題にのぼりやすくなりました。台風1号とか。
いつの世であっても、是非を問うのも下すのも、結局は人なんでしょうね。人をつくるとか、人造人間。今はAIに相当でしょうか。 - ちゅみ 16-07-08 (金) 16:04
-
お若くして天皇となられ、昭和を生き抜かれた昭和天皇。
いつの時も国民の幸せを第一に願って下さっておられたエピソードが山と聞かれます。
歌詞に祈りの深さを感じます m(_ _)m - 管理人 16-07-12 (火) 23:10
-
ブーシュカさん
興味があったらユーチューブで検索してみてください(´ー`) さらに興味があったら雅楽を勉強してみるとか。確実に神道と繋がっていますから、別の角度からいろんな副産物がついてきますよ~習っている人口が少ないので、若い方は大切にされます!
ちゅみさん
ほんとうに良い歌詞ですよね。昭和生まれで身近?でもあってか、昭和天皇って自分の中では「キングオブ天皇」って感じ。人間臭さがより一層、天皇としての姿を輝かせてくださっています。